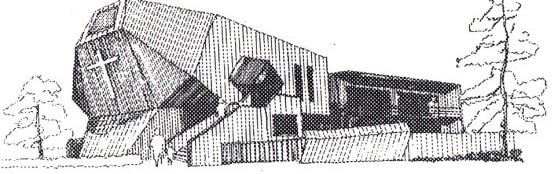〈季節〉
1章14~19
「神は言われた。『天の大空に光る物があって、昼と夜を分け、季節のしるし、日や年のしるしとなれ。天の大空に光る物があって、地を照らせ。』そのようになった。神は二つの大きな光る物と星を造り、大きな方に昼を治めさせ、小さな方に夜を治めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて、地を照らさせ、昼と夜を治めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見て、良しとされた。夕べがあり、朝があった。第四の日である。」
物語は、神が大空に二つの光る物を造ったと語る。その二つは「太陽」と「月」のことであるが、ここでその名は出されていない。
古代オリエントにおいて、太陽と月は神を指し示す代名詞であったという。当時の権力者たちは太陽礼拝・月礼拝を用いて自身を「太陽から生まれた子」、「月から生まれた子」であるとし、「神の子」としていた。
創世記の原初史物語の作者はここで、太陽と月の名を出さず、ただ単に「光る物」とした。ここには物語作者の意図があったとおもわれる。太陽礼拝・月礼拝を用いて権力者たちが自分を神にしていたその偶像崇拝に対する否をこういう仕方で表したのではないかとおもわれる。
原初史物語作者はここで「偶像崇拝」の拒否を語っているが、その拒否にこめた根本理由は次のところにあるとおもわれる。地の世界に絶対というものを認めないということが偶像崇拝に対する否であるが、この絶対を作ってこれを崇拝させる偶像崇拝に対する否は、個の存在の意味を確立してゆくとき必須の課題となる。絶対的なものがある社会では個の存在の意味は奪われ、失われてゆく。原初史物語の作者が偶像崇拝を拒否すべしと語った根本理由は個の肯定と確立を可能にするためにあったとおもわれる。
ここで、注目しておきたいことは原初史物語作者の姿勢についてである。物語作者はこの二つの光る物についてこうしるした。「それらは季節のしるし、日や年のしるしとなれ。」原初史物語の作者は、太陽と月には季節を示すという役割が与えられているとする。ここには、この原初史物語作者の姿勢が示されている。
太陽や月が礼拝の対象になっており、原初史物語の作者はこの限りにおいてこれを拒否するのであるが、太陽や月の存在を否定せず、むしろそれらは有用なものであると位置付けている。ここには原初史物語作者が冷静な姿勢にあったことが示されている。
物語作者は、当時は神の位置にあった太陽と月を被造物であると言い切った。被造物であると言い切るということは、神として崇拝の対象としている世の価値観を否定するということである。この物語の作者は否定すべきことは否定する。しかし、この物語作者は存在そのものを否定せず、その存在が神の創造の世界において神から与えられている位置と意義を提示する。
ここで物語作者は、人々が素朴にみとめ肯定している宇宙の秩序を人々の支配するために巧妙に利用する国家が圧倒的力を持っている現状の中で、その国家のありようには「否」を言い、人々が素朴にみとめている宇宙の秩序、それは太陽と月が「季節を知らせる」という宇宙の秩序であるが、それについては肯定する、この冷静さを持っていた。
さて、ここで原初史物語作者の言う、太陽と月に与えられている役割の「季節を知らせる」について、これが何を意味するかおさえておきたい。
まず、この「季節」ということが創世記の原初史物語において重要なテーマとなっているということを承知しておきたい。
創世記において「季節」ということが再び登場するのは、8章の終わりのところである。そこにはこうしるされている。
「地の続くかぎり、種蒔きも刈り入れも、寒さも暑さも、夏も冬も、昼も夜も、やむことはない。」(8章22)
ここにしるされていることは要するに、「季節」が無くなることはないということ。原初史物語の作者は、創世記1章で述べた「神が季節を造った」を8章の終わりのところでいまいちど神が造った季節は無くなることはないということを確認する。
この創世記8章の終わりのところであるが、ここは8章から始まった「洪水物語」が終わるところ、地を覆っていた大量の暴力的な水が無くなり、地が乾いた状態に戻るところである。ここは、言い換えると、地がいまいちど新しく始まるという場面である。
原初史物語の作者は、その地が新しく始まる場面で神がまず為したことは季節が無くならないようにすること、季節があり続けるようにすること、季節が新しく始まるようにすることであった、と語る。
創世記の原初史物語が物語のテーマとして「季節」を掲げている、これがここで明らかになったが、そこで確認しなければならないことは、この原初史物語のテーマの「季節があり続けるように」とは内容的には何を言っているテーマであるのかということについてである。
創世記1章14に「季節のしるし、日や年のしるしとなれ」とある。これは「歳時暦」のことを言っている。この歳時暦は食べ物をつくる農にとって必須のもの、食べ物をつくる農は歳時暦に沿っておこなわれる。この歳時暦は季節のことである。季節は歳時暦において示される。季節は食べ物をつくる農にとってなくてはならないものである。
そうすると、原初史物語作者の語る天と地の創造物語の第四の日に扱われているのは神が歳時暦を可能にしたということであるが、これは神が季節を造ったということ、すなわち食べ物をつくる農を成り立たせる環境を神が創造したということ、こう言ってよい。
ここから先は、わたくしの推測であるが、申してみると、
創世記の原初史物語の作者はバビロン捕囚の中にあり、捕囚からの解放を待ち望んでいた。その解放の実現はあの「出エジプト」のときと同じように、モーセのような人物が現れることによって可能となると信じていた。ここで、しかし、或る問題が生じていたのではないかと推測される。それは、メシアの登場を待望する中で「息切れ」という問題、それが生じていたのではないかと推測される。
創世記の原初史物語の作者は創世記8章の終わりのところで、すなわち「洪水」の「水」が引き、地が新しく始まろうとするその場面で、神は何をなさったか、それは季節があり続けるようにすること、すなわち「食べ物をつくることが持続的にできるようにすること」、と語った。
この語りは、捕囚の中の民が解放への長い道のりを歩き通すことができるために、そこで生じる「息切れ」問題を乗り越えなければならない、そのために神は食べ物が持続的にできる環境を備えてくださっている、と、原初史物語の作者は疲労困憊する捕囚の中の民に語った、ここはそういう語りであったのではないか、と推測される。
聖書が言っている神による救済には二つのことがあるようだ。一つは「ノア契約」においてみられるもの、いま一つは「アブラハム契約」においてみられるものである。
後者の「アブラハム契約」においてみられる神による救済であるが、これは神がいろいろな仕方を通して起こす「救済解放の出来事」という特徴がある。前者の「ノア契約」においてみられる神による救済であるが、これは「全ての命の保全」という特徴がある。
聖書の神による救済の主流は「アブラハム契約」にみられるところの「救済解放の出来事」にあると言ってよいとおもうが、しかし、「ノア契約」にみられるところの「全ての命の保全」という仕方の神による救済、これを軽くみてはいけない、いや重要なものとみてゆかなければならないのではないかとおもわれる。
原初史物語の創世記1章はこうなっている。
神による創造の二日目は、水を限定的に置く天の創造であるが、これは神による創造の四日目にしるされる農を可能にすることへの配慮である。
神による創造の三日目は、水のない乾いた地の創造であり、その地に対する植物を芽生えさせよとの委託が語られ、また水を限定的に置く海の創造がおこなわれるが、これは神による創造の四日目にしるされる農を可能にすることへの配慮である。
神による創造の五日目は、太陽と月の創造である。これは神による創造の四日目にしるされている食べ物をつくる農を可能にすることへの配慮である。
このようにして、原初史物語の創世記1章は、食べ物をつくる農を可能にすることへの配慮を語っている、と言ってよい。
ここで、一冊の書物を紹介したい。それは、『沈黙の春』と題されている書である。
この書は米国で発行され、大きな話題となり、影響を与えた。この書は米国においてだけではなく、工業先進国と言われている国々にいる人々に強い影響、刺激を与えた。工業先進国にいる人々が環境問題への真剣な取り組みを始めたのは、この書からであったと言っても言い過ぎではない。この国日本においても、この書はいち早く翻訳出版され、強い影響と刺激をもたらした。
この書『沈黙の春』はこう問いかけている。
春が来ると自然の世界は新しい芽が出、緑が一面に生え、花が咲きほころび、鳥がさえずる、いわば、春というのはにぎやかな世界となるのだが、春が来ても静まりかえっている、春は色々なものが楽しげにおしゃべりする季節であるが、みんな黙りこくっている、沈黙の春となっている、春という季節が無くなってしまったかのようだ、どうしてだろう。
この書の著者はレイチェル・カーソンという米国の生物学者にして生物ジャーナリスト。この書が発行されたのは1962年、50年余前である。彼女はこの書において、春が沈黙の春となっているのは人間が自然に対し暴力を加えたことが原因であると言い切っている。この指摘は生物科学者としての緻密で冷静な調査と研究に基づいたものである。
彼女は人間が自然に対して加えている暴力の事例として、まず化学薬品を挙げているが、それに加えて放射能による汚染について、この時点で言い及んでいる。彼女は先を見通していた。
彼女は熱く語る。このまま行けば食べ物ができる環境が失われる、食べ物が持続的に作られる環境が失われる、この地上世界は人間のためだけのものではない、生きとし生ける全てのもののためのものである、このまま行けば命の根源である食べ物ができる持続的な環境を人間が壊す、絶つ、終わらせてしまう、それはしてはいけない、と、熱く語っている。
彼女はこの書の出版の2年後に他界、57歳の若さであった。もっと長く生きておられたら、さらなる一層の刺激的な書をわたしたちに送り出してくださったことであろうと、彼女の早過ぎた他界が惜しまれてならない。
レイチェル・カーソンの『沈黙の春』を読んで、もしかしたら彼女は、聖書の創世記にしるされていること、すなわち神は季節を造った、人は季節を無くすことをしてはならない、これを創世記から聴き出していたのかもしれない、とおもった。
わたくしが創世記の原初史物語にこのようなメッセージが語られていることを知ることになったのは、有機農法の方々との出会いを通してであった。この出会いのことについては別の機会に申してみたい。
ところで、ここの創世記1章14~19の文脈の中に「星」が造られたということが出てきている。ここで、「星」が造られたことに言及した物語作者の意図するところを探っておきたい。
ここで、「星」が造られたと述べるこの言及の意図は、星もまた被造物であるということ、つまり星は神ではないということを言うためであった。
ここで〈申命記4章18〉にしるされているところを参照しておきたい。そこには、偶像礼拝の対象として、太陽と月に加えて星が言及されている。
古代オリエントでは、星は運命という考え方と結びついていた。古代オリエントの人々の時間意識は星(天体)の運行によって規定され、人間界は個々人の運命に至るまで星の運行に支配され、定められているというものであった。古代オリエントの人々は、人の運命は星の運行によって規定されているとする運命信仰に組み入れられ、星(天体)を神として崇拝する信仰から脱出することはできないでいた。
原初史物語の作者を含むイスラエルの民は、この「運命」という考え方は受け入れてはならない、これは拒否しなければならない考え方であるとしていた。
その理由は、出エジプトによって始まったイスラエルは神による導きによって立ち、歩む存在であって、神ヤハウェの呼びかけがあれば、それには応じる用意があること、つまり今を変える用意があること、これを基本としていたのであり、運命なるものがあってこれに規定されて生きるという考え方は、自分たちの自分たちであることに反するもの、これを崩壊させるものであったからである。
イスラエルの民は、神ヤハウェの導きによって立ち、歩むとするこの自分たちの存立の基盤、これを崩壊させる星(天体)礼拝を退けるのに、相当のエネルギーを費やしたようだが、創世記の原初史物語の作者も、「星(天体)礼拝」の運命信仰を退けるために相当のエネルギーを費した、と推測される。
ここで興味深いことを二つ挙げる。
マタイ福音書のイエス誕生物語に、東の方からやって来た占星術者たちがイエスに拝礼する場面がしるされているが、この物語は「星(天体)礼拝者」がその「星(天体)礼拝」を放棄する回心物語である、と言ってよいかとおもわれる。
いま一つは、ガラテヤ書4章8~10のパウロの言葉である。
「あなたがたはかつて、神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし、今は神を知っている、いや、むしろ神から知られているのに、なぜ、あの無力で頼りにならない支配する諸霊の下に逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなたがたは、いろいろな日、月、時節、年などを守っています。」
ここでパウロは、「律法への奴隷」になることは「神々への奴隷」になることだとしているが、さらにその「神々への奴隷」になることとは、「いろいろな日、月、時節、年などを守る」ことであるとしている。
当時のギリシャ世界(ヘレニズム)において広まっていた暦(カレンダー)を遵守する慣習はユダヤ教においても一般的なものとなっていたようである。この当時、暦の定めを遵守することは、宇宙の中に働いている霊力に逆らわないこと、宇宙の定めに調和すること、宇宙の霊力の復讐を未然に防ぐ手段であることを意味していた。
この風潮にキリスト者が同調してゆくのを見たパウロは、これは「神々への奴隷」になることであり、「律法への奴隷」になることであると、激しい調子で語っている。このパウロと、星(天体)礼拝の拒否を通して運命信仰の拒否を主張する創世記の原初史物語作者とは、内容的に重なるところがある。
新約聖書のパウロは、当時の「暦への順応」を「神々への礼拝」とし、「偶像礼拝」とし、これを「律法への奴隷」であるとしたが、このパウロの言うところは、今日において示唆深いのではないか。
現代人の多くは、運命論のごときものに関わり合っていないし、それに陥っていないと考えている。しかしはたして、そう言い得るか。
既存の秩序・慣行・社会通念に縛られ、個の人権が奪われるということ、これは今日の社会に起こっている。このことは、今日の社会の既存の秩序・慣行・社会通念が、古代の人々を縛っていた宿命論と同じ機能をはたしているゆえに起こっていることであると言ってよいのではないか。これはパウロの言う「律法への奴隷」という状況であると言い得るのではないか。
原初史物語作者が「星礼拝」の運命信仰を退けるこの物語は、今日のわた
したちに重要なメッセージを発している、と言ってよいのではないか。